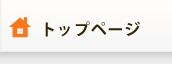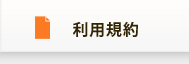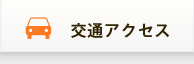周年記念や特別な大義が無い限り 大きな予算は付かないし掛けられない
これが市民劇(ミュージカル)です また地域の理解がなければ続きません
仮に製作費用が増えれば 出演者に十分な訓練や指導が可能となり
創造環境を整えることだって出来る
舞台づくりに至っては 時代考証の伴う衣裳や小道具の調達
大手資本の商業演劇や立派な劇団等と比べる必要はありませんが
見栄えのする豪華セット等も仕込めます
何より支える市民スタッフは 殆どがボランティア有志の方々
準備期間は週末返上で運営にあたる
そうまでして続けられるのは 地元愛と奉仕精神の賜物だと思います
この心もちが崩れたら 市民劇(ミュージカル)の成立は難しく
継続は困難となるでしょう ケアせずこのまま放ってはおけません
補助金やクラファンなど 資金調達の手立ては色々あるものの
必ず実現する訳ではありません お金が全てとは言いませんが
必要とする製作費があれば 劇世界がもっと広がるのは言わずもがなです
この国の偏った予算配分のツケは 地方文化にも少なからず影響を及ぼします
今こうして毎年休むことなく 続けられたことを振り返り
経済も踏まえ 運営スタッフや出演者の関わり方など
様々なパワーバランスを見回し 私なりに15年を検証している最中です
今回作品で取り上げた若月俊一先生は 医療現場に文化を持ち込み
コミュニケーションの大切さを通し 地域交流や社会貢献を果たされました
演劇を使った市民ミュージカルもまた 地域で起こっていることを知るばかりか
コロナ下で喪失した人の距離感を縮め 交流や相互理解のツールとして
益々その必要性と価値の高まりが 求められるべきではないでしょうか
佐久市の市民ミュージカルは 地域の皆さまが作り支える文化財です
これ迄の轍(わだち)を確かなものとし 様々な困難を乗り越えた先に
新しい道が繋がることを願ってやみません
公演の幕がおり まだ熱量が残る今だからこそ
敢えて現状を綴らせていただきました 一緒に考えていただけたら幸いです